Local Stories and Daily Life from Nagoya
パンダらーめんの台湾ラーメン ─ むせても食べたい欲望

「パンダの台湾」が切れたら、
生活がちょっと乱れる。
名古屋・千種区と名東区の境目。
光が丘の坂をくだった猪高車庫近くに、
ひときわ目立つ赤い看板がある。
控えめどころか、
どストレートに「パンダらーめん」と叫ぶ店。
最寄り駅からはどこからも遠く、
車がないと気軽に行けない、
ちょっとした孤島のような場所。
それでも足を運ぶ人がいる。
ここにしかない味があるからだ。
笹田裕之さんにとって、
この店の台湾ラーメンは、生活の隙間に入り込み、
日々の調子を整える“自分の軸”のような存在である。
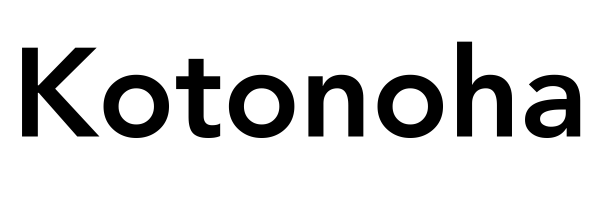

Kotonohaの「偏愛シリーズ」では、
人が“好きすぎて離れられないもの”を手がかりに、
その背景にある日常のリズムや、小さなこだわり、
暮らしの奥にひそむ物語を静かに描いていきます。
今回は、名古屋・千種区のはずれにある
パンダラーメンの台湾ラーメンと笹田裕之さん。
パンダの台湾ラーメンを食べ続けてきた
笹田裕之さんの“好きすぎる理由”をたどると、
偏愛という言葉では足りない、
生活の温度や、彼自身の揺れない軸が
そっと立ちあがってきます。
迷わずメニューは一択

パンダのキャラクターが貼られた窓ガラス越しに、
ふわりと中華屋のにおいが流れてくる。
厨房の湯気、鉄鍋の音、 炒め油の香りに少しだけ混ざるスープの湯気。
どこにでもありそうで、
なのにここでしか漂わない空気がある。
笹田さんは迷うことなく、
「台湾ラーメン。ジャンボで。」
「ここに来たら、これ以外は考えられないんですよ。」
声は小さく落ち着いているのに、
芯だけが熱を帯びていて、
少し可笑しいくらい真剣だった。
「ジャンボでたっぷり台湾補給しておかないと」
その真剣さの理由は、
目の前の丼の中に静かに現れる。
“パンダの台湾”は、
他とは一線を画す。

「見た目がまず、普通の台湾と全然違うんですよ。」
そう言って笹田さんは、
湯気の奥に沈む丼をじっと見つめる。
持ち上げた黄色い卵麺の下には、
これでもかというほどの挽肉が、
甘辛いスープをまといながらたっぷり沈んでいる。
「挽肉の量がね、まずおかしいんです。
ひき肉ラーメンと言ってもいいくらい。
麺より“具”を食ってる感じなんですよ。」
麺をすすると、甘辛い熱がふわっと鼻に抜ける。
とはいえ、よくある“濃厚台湾”とはまったく違う。
「重たくないんですよ。旨みがしっかりあって、
一気に食べちゃうタイプだね。」
具材も独特だ。
「で、野菜がニラともやしじゃなくて、
にんにくの芽と薄いにんじん。これがまた絶妙で。
この甘辛スープと合わせると、妙にクセになるんですよ。」
麺と挽肉と野菜をまとめて口に入れると、
一瞬、呼吸が甘くなる。
その“呼吸の甘さ”が危険だ。
笹田さんは、急に真剣な顔になる。
「めちゃくちゃうまいんですけど…
素人は絶対むせます。」
——むせる?

「激辛じゃないんですよ。
辛さでむせるんじゃなくて、
“うまいからかき込みたくなる”んです。
で、挽肉とスープの熱が変なタイミングで喉に入って—— もう100%むせます(笑)」
唐辛子の粒が飛び込むような刺激ではない。
むしろ、甘辛い挽肉の“熱の勢い”が喉の奥で予想外のカーブを描く感じだ。
気を抜いて食べれば、
ほぼ間違いなく咳き込む。
でも、一度むせてもまた食べたくなる。
偏愛を語る人の目は、
ラーメンの湯気よりも熱い。
行けなかった一年

笹田さんがこの店に通い始めたのは、高校時代。
気づけばもう25年以上足を運んでいる。
最初から台湾ラーメン一択だったわけではない。
当初は別のメニューを頼んでいたはずなのに、
ある日ふと台湾ラーメンを口にした瞬間、
スイッチが入ったように、そこから沼に落ちていった。
「なんか…気づいたらここばっか来てたんですよね」
理由を聞いても、きれいな理屈は返ってこない。
ただ、体と気持ちが自然とここを求める。
そういう“出会い”だったのだ。
ただ、そんなに愛している台湾ラーメンなのに、
この一年は仕事の都合とパンダの特殊な営業時間で、
ほとんど店に来られなかった。
パンダラーメンは
土日・祝日・金曜夜が人手不足のために休みという、営業体制。
「愛顧を込めてホワイト企業って呼んでます(笑)」
そう笑って話すが、
行けない日々は本当にきつかった。
「体が欲しすぎてやばかったですね。
夢にも出るし、匂いの幻覚みたいなのも感じるし。
他の人の写真を見ると痛いんですよ」
偏愛という言葉では
追いつかないほどの執着だった。
さらっと始まる、パンダ論
まるでアスリートのように、台湾ラーメンと無心で向かい合い、麺と挽肉とスープを一気にかき込む。
食べ終えたあと、水をひと口飲んで店内を見回しながら、ぽつりと言う。
「ここ、意外にカップルのお客さんも多いですよね。」
ただの感想のようでいて、
その後に続く言葉は妙に核心をついてくる。
「パンダに一緒に来てるって時点で……
まぁ、将来の相手ですよね。」
さらっと言うのに、なぜか説得力がある。

「ここって、本質見せる場所なんで。
自分のテリトリーに相手を入れるっていうか」
家族に会わせる感覚に近いのかもしれない。
「ここに連れてきてる時点で、もう大事な人ですよ。」
そう言いながら、何気なく視線を店の外へ向ける。
「ただね——
この店に恋人連れてくるって、実はハードル高いんですよ」
——え?
「駐車、めちゃくちゃムズいんで(笑)
スペースが超タイトで、出口は坂が急でほぼ擦りますから。初めて来る人は絶対気をつけたほうがいい。」
まるで試練みたいな言い方だ。
笹田さんはさらに続ける。
「あと、裏口から出入りしてる人は相当な通ですね。
あそこを自然に使えるって、かなり来てる証拠です」
台湾ラーメンと、駐車の技術と、裏口の存在。
この三つを当たり前のように語るその姿が、
なぜか少しだけかっこいい。
ただの一杯じゃない
生活の“調子を戻すスイッチ”
笹田さんにとって、
パンダの台湾ラーメンは単なる外食ではない。
行けないとしんどくなり、
食べると体の調子が戻り、
店の空気が静かに生活を整えてくれる。
そしてその偏愛は、
他の誰にも揺らされない。
「まぁ、とにかく一回食べてみてください。
多分わかると思います」

静かな声なのに、
確信だけは強い。
偏愛の話は、
結局いつも“その人自身”の話になる。
今日もまた、
狭い駐車場の奥で、
ジャンボ台湾ラーメンの湯気がゆっくりと立ちのぼる。
その奥にはきっと、
笹田さんの“揺れないもの”が息づいている。
パンダらーめん 猪子石店 愛知県名古屋市千種区千代ケ丘6-10 平和ビル1F
